この記事を読まれる方は、近藤紘一さんの作品に触れ、あるいはノンフィクション作家の沢木耕太郎さんの文章(最近では「作家との遭遇」に収録)等から興味をもたれて検索された方が多いかと思います。近藤さんの作品は非常に魅力的ですが、「サイゴン」という街がホーチミン市と名を変えてからも随分と時間が経ち、インターネット上の情報もあまり多くはありませんでしたよね。
この記事では、以下のことについて解説していきます。
- 近藤紘一の作品について
- 近藤紘一の経歴について
- 近藤紘一と「サイゴンから来た妻」の現在は?
近藤紘一についてもっと知りたいと思われた読者の方のために、近藤さんの全作品を読破し、関連書籍も購入して調べた私の知り得た情報を共有したいと思います。これらの情報が、より作者の作品を楽しむ一助となれば幸いです。
・・・東南アジアの魅力を生み出すものは、多少重複するがこの地域のそれぞれの国で見られる人間らしさである。新聞記者と言うむしろ「現象」を追う身でありながら、そこで見る私の興味は、実際にこの地域で生きる人々の生き方やその喜怒哀楽といったようなものに注がれ続けた。
(妻と娘の国へ行った特派員 あとがきより)
《参考》旧ブログについて
近藤紘一さんをメインテーマとしたブログ「Witness1975’sblog」を書いていました。旧ブログの内容も現在移行中ですが、こちらでは編集、再構成してわかりやすく、より深くお伝えできればと思っています。書き加えていきますので見守っていただければ幸いです。また、コメントいただければ大変励みになります。
近藤紘一の全作品一覧。代表作は「妻と娘」3部作
サンケイ新聞社のサイゴン特派員であった近藤さんは、1975年に南ベトナム共和国の崩壊を見届けました。「サイゴン陥落」として知られる、ベトナム戦争終結の一部始終です。 近藤さんは、ジャーナリストとして、ベトナム、インドシナ及び東南アジア地域の情報を伝え続けました。作家としての活動期間は1975~86年の11年間で、全著作は9作品です。

- 1975 『サイゴンのいちばん長い日』
- 1978 『サイゴンから来た妻と娘』
- 1978「統一ベトナムとインドシナ(新書)」
- 1979 『悲劇のインドシナ・戦火と混迷の日々』
- 1980 『バンコクの妻と娘』
- 1982 『したたかな敗者たち』
- 1985 『パリへ行った妻と娘』
- 1986 『仏陀を買う』
- 1986 『目撃者―「近藤紘一全軌跡1971~1986」より』
その他に3冊、共著、翻訳の作品と、「サイゴンから来た妻」である近藤ナウさん名義の作品があります。
- 共著 1984 『国際報道の現場から』古森義久との共著
- 翻訳 1978 『野望の街』(ハロルド・ロビンス著/翻訳)
- 1978『アオザイ女房』近藤ナウ
サンケイ新聞記者、作家近藤紘一の経歴は?
近藤紘一(1940-1986)は、東京都出身のジャーナリスト、作家。サンケイ新聞の特派員として、「サイゴン陥落」を見届け、そのベトナム戦争終結の場面を「サイゴンの一番長い日」として刊行した。
インドシナ地域を中心に国際報道に携わりながら、ベトナム出身の妻と娘との生活を描いた「サイゴンから来た妻と娘」等の作品を生み出す。同作が第10回大宅壮一ノンフィクション賞を沢木耕太郎の「テロルの決算」と同時受賞するなど活躍した。
幼少期~サンケイ新聞入社(~1964年)
医師である父近藤臺五郎の長男として生まれる。5歳のときに終戦、神奈川県逗子市で育ち、少年期には流鏑馬の稽古に励む。湘南高校を経て早稲田大学仏文科に進学し、首席で卒業後、サンケイ新聞に入社、静岡支局勤務となる。翌年、駐仏大使萩原徹の長女浩子さんと結婚する。
フランス留学~サイゴン勤務(~1971年)
海外留学生として夫婦でパリに渡る。同時に特派員として「プラハの春」を取材する。帰国後の1970年、夫人と死別する。1971年30歳の時、南ベトナムのサイゴン支局長として赴任。
サイゴン勤務~サイゴン崩壊(~1975年)
ベトナム人のナウさんと出会い、1972年再婚。娘のミーユンほかの親族とともにナウさん所有の「幽霊長屋」に暮らしながらベトナム問題をレポートする。開高健、司馬遼太郎等を現地で迎えるなど、サイゴン支局長としての任期は最長となる。1974年に一時帰国するも、戦況の悪化を受けてサイゴンに戻り、サイゴン陥落を目撃する。
バンコク勤務~帰国(~1983年)
日本へ帰国後、「サイゴンから来た妻と娘」を出版、その後1978年にバンコク勤務となる。引き続き東南アジア地域についてレポート。カンボジアのポル・ポト政権下のキリング・フィールドを生き抜いた日本人女性の体験談を取材した「悲劇のインドシナ・戦火と混迷の日々」、「バンコクの妻と娘」等を執筆する。
帰国後(~1986年)
古森義久と共著で「国際報道の現場から」を刊行。小説の執筆も始め、初小説「仏陀を買う」が中央公論新人賞受賞。1985年、体調を崩し入院、1986年1月27日、胃がんのため虎の門病院にて息を引き取る。
途上の死
沢木耕太郎は、近藤紘一の死を「途上の死」と評した。まさにこれから、だったのだ。ここに記した文章は、全く彼の魅力といったものを表してはいない。わずかな活動期間の中で彼がどのように豊かな文章群を残したか、その原文を確かめて頂ければ幸いである。
衝撃結末?近藤紘一と「サイゴンから来た妻」の現在は?
1975年4月30日、サイゴン陥落ー。
長く続いたベトナム戦争の終結を見届けた新聞記者、近藤紘一は、サイゴン陥落直前の状況を次のようにレポートした。
サイゴンはいま、音を立てて崩壊しつつある。つい二カ月前、いや一カ月前まではっきりと存在し、機能していた一つの国が、いま地図から姿を消そうとしている。信じられないことだ・・・
(「サイゴンから来た妻と娘」より)
サイゴンのいちばん長い日
近藤さんが目撃することとなった南ベトナム共和国崩壊の瞬間と「その後」は、大宅壮一の編集した「日本のいちばん長い日」になぞらえて、「サイゴンのいちばん長い日」として刊行された。
しかし、サイゴンで人々の暮らしに溶け込みながら日々を過ごしていた近藤さんにとってのその一日は、「長くて短い日(あるいは短くて長い日)」と感じられたという。近藤さんは、「現在をもってそちらの業務を停止し、脱出に全力を尽くせ」という絶対社命を受けながら、自らの意思でその激動の中に身を置き、歴史の目撃者となることを選んだのだ。
もう一つの物語
そして、この事実とは別に、近藤さんにはもう一つの物語があった。この物語こそが「サイゴンから来た妻と娘」である。近藤さんにとって2作目の作品となったこの本は、1975年4月9日、戦況の悪化するサイゴンから南ベトナム国籍の妻、ナウさんを日本に送り返す場面から始まる。南ベトナム唯一の玄関口であるタンソンニュット空港が陥落すれば、ベトナム国籍の彼女の出国は困難になるだろう、と思われた。
8か月前の74年8月、近藤さんは、サンケイ新聞サイゴン支局長としての任期を終え、妻であるナウさん、娘のユンちゃんとともに日本に帰国していたが、戦況の悪化を受け、社命によりサイゴンに戻っていたのだ。
日本に娘を残し、妻を先に帰国させた近藤さんは、前述のサイゴン陥落の一部始終を見届け、24日後に出国記者専用機で日本に帰着することになる。いわば「サイゴンから帰ってきた夫、そして父」として、日本で過ごす近藤一家の日々が、「サイゴンから来た妻と娘」に収められている。
サイゴンから来た妻と娘
当時は今よりずっと国際結婚の珍しかった時代である。1970年代前半、沢木耕太郎が後に「深夜特急」として描かれる旅をしていた頃、外国に向かう人にカンパをするというのも不思議なことではなかったと思われるし、インターネットのない時代に異国に触れるカルチャーショックというのは、現在の比ではない。
しかし、描かれるのは、ベトナム式子育て法・食生活といった文化の違いだけではなく、祖国を失った妻、思春期を迎える娘との日々の暮らし・・・暖かく、ユーモアに溢れた家族の記録である。この暖かさには普遍的なものがあるのではないか、と思う。
「サイゴンから来た妻と娘」衝撃の結末は?
さて、この記事の見出しには「結末」という文字を使用した。yahooやGoogleの検索窓に「近藤紘一」と打ち込むと、近藤紘一とその家族に訪れる「衝撃結末」という情報がヒットするからだ。そのような結末は実際なかったのではないか、と思われるし、両論併記に当たるものとして、この記事にも多少なり存在価値があるのではないだろうか、と思う。
30年以上も読み継がれる近藤紘一の作品には、ある種の力があり、魅力があるということは間違いがないように思える。私たち読者の正しい態度は、近藤さんの描く家族の物語を、近藤さんの描くそのままに受け取ることではないか。
これからの読者へ
この記事には「続き」があります。しかし、これから「サイゴンから来たと妻と娘」を手に取ろうとし、あるいは近藤紘一の他の作品を読もうと思われる方には、この記事の続きよりも、とにかく近藤さんの残した「原文」を読んで頂きたい、と思います。
この素晴らしい新聞記者、作家である近藤さんの作品はあまりにも少なく、近藤さんの精神に触れる術があるならば、それは近藤さんの作品を熟読玩味すること以外にはないようです。しかしながら、この記事が私にとっても、あるいはあなたにとっても、近藤さん作品の本当の魅力に触れる一助になれば、と願っています。
【続き】
言葉への願い
・・・「サイゴンから来た妻と娘」は、「バンコクの妻と娘」、「パリへ行った妻と娘」へと続いていく。近藤さんはインドシナ地域の優れたウォッチャーとして取材活動を続けて行くとともに、ある信念を持って娘を育てた。それは決して、娘を「祖国を亡くした根なし草(デラシネ)」にさせない、ということだ。
かつてフランスの植民地であったベトナムの学校において、ごく初歩的なフランス語を習っていた娘をフランス語学校へ進めると、ときには厳しく娘にフランス語を叩きこんだ。
途上の死
やがてユンちゃんは立派に成長し、フランスの大学進学試験に相当する「バカロレア」に合格するまでになる。あるとき、まだ成人しない「パリへ行った娘」のために、ナウさんもパリに向かった。
この頃、ナウさんはパリでアパートを買い求め、娘とともに暮すことになる。ここを娘時代のナウさんの彼氏であったという「ボロー氏」が訪れていることが、「パリへ行った妻と娘」において描かれている。おそらくこうした出来事を指して、近藤さんが日本に取り残され、妻と娘がパリで知らない男と暮らしている「衝撃結末」というデマのもとになったのではないかと思う。
しかしながら別の理由で・・・近藤紘一を語り手とする暖かな家族の物語は、近藤さんの早すぎる死によって一度幕引きをすることになる。
エピローグ
しかし、我々読者と同じように、現代のパリで暮らしている彼ら彼女らの生活に、「物語には結末がある」という理由で、結末を設けるならば、事実としてこのようなエピローグが語られるかもしれない。
大人の女性となったユンちゃんは、やがて作中に登場するフランス人の青年ピエールと結婚し、二人は男の子をもうける。
彼の名は、ジュリアン・コウイチ。
近藤紘一の孫である。コウイチの物語は、今も続いている-と。
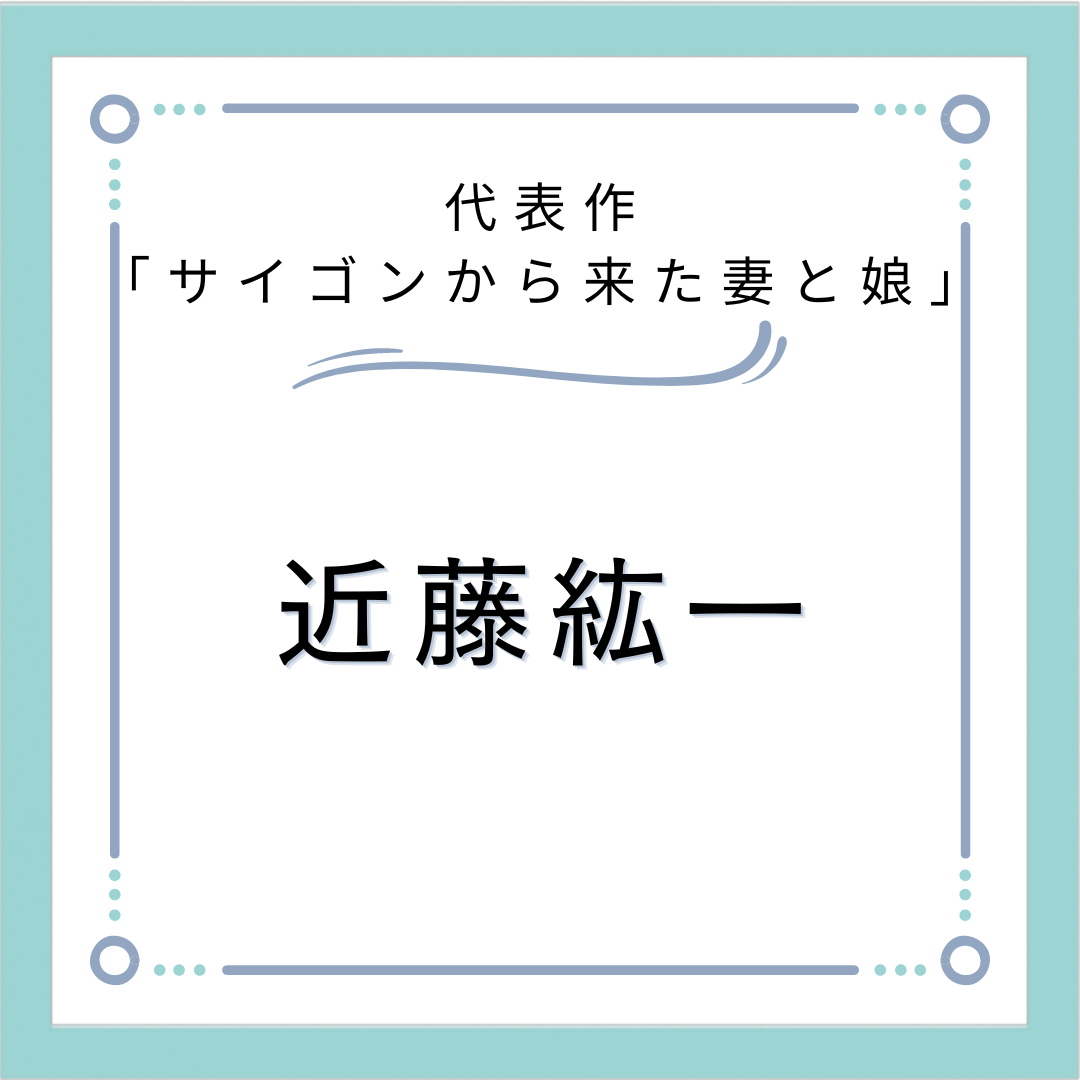

コメント